2011�N4��8��(���j ���m�V���[�� ��Ђ����q��𔐓���
�匎�� ���낵���ւ�i���������Z���^�[�j
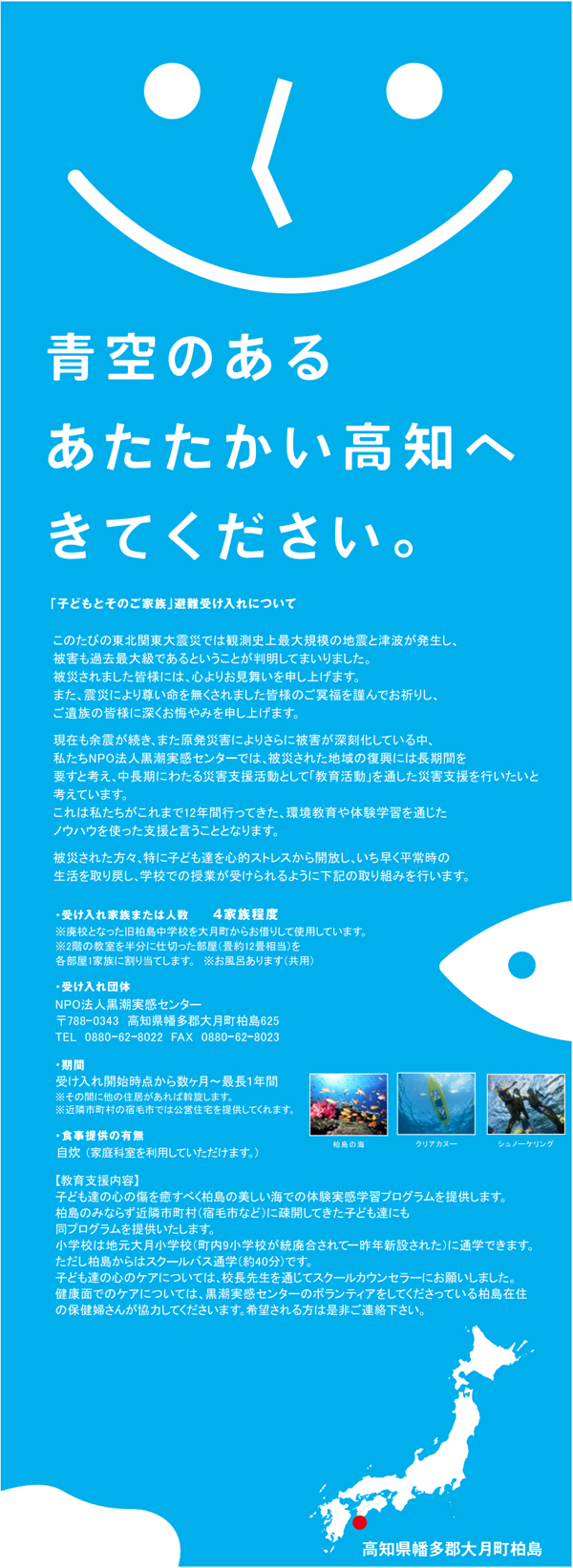
��Вn�̎q��ɍ��m�ɑa�J���Ă��Ă��炨���Ƃ̎v�������߂č�����E�F�u�|�X�^�[�̈ꕔ�i���́E�~���f�U�C���������j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Ђ����q��𔐓���
�@�܂��ŏ��ɁA�����{��k�ЂŔ�Ђ��ꂽ�F�l�ɁA�S��肨��������\���グ�A�܂��A�S���Ȃ�ꂽ�F�l�̂����������F�肵�܂��B�����č���́A���������������Z���^�[���l�����s���悤�Ƃ��Ă���A��Ђ����q�ǂ���̎���Ȃǂ́A�ЊQ�x�������Ȃǂɂ��ĕ��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ռ��̉f��
�@3��11���ߌ�2��46���B���̓��̔����́A���͂�����̂̕��i�ƕς��Ȃ������B�������͎������Ŏd�������Ă����B�X�^�b�t�̉�������̌g�т������B���Ɍ��ɏZ��ł���ޏ��̉Ƒ����炾�����B�u�������n�k�������ăe���r��������A���k�ő傫�Ȓn�k���������݂��������ǁA�������͑��v�H�v
�@�}���Ńe���r�������B���{�n�}���\������k���݈�ɒÔg�x���߂���A�A�i�E���T�[�����ӂ��Ăт����Ă����B�e���r��ʂ͋{�錧�̋��`���ӂ̊C���f���Ă����B���������̂Ƃ��낪�h��Ȃ������������A����قǑ傫�ȒÔg������Ƃ͎v�������Ȃ������B
�@����������A���ʂ��������ɍ����Ȃ�ݕǂ��痤�ɐ����͂��オ���Ă����B����悠���Ƃ����Ԃɑ傫�ȒÔg�����X�ɉ����A��^���D��A���D�̌W�����[�v����A�D�����X�Ɨ����ꗤ�ɑł��グ��ꂽ�B���̌�Ƃ�ԁA����Ƃ�������̂��u���Ԃɍ����g�ɂ̂ݍ��܂�A�|�M�������i��ڂɂ����B
�@����͍��A�{���ɓ��{�ŋN���Ă��邱�ƂȂ̂��H�ɂ킩�ɂ͐M�����Ȃ������B���X�Ɖf���o�����Ռ��̉f���ɖڂ������t���ɂȂ�A�e���r�̑O���痣����Ȃ������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�����{��k�Д�Вn�̗l�q�B�����̏�Ɏ��c���ꂽ�A���D�@�@�@�@�@�@�@�@�i��茧��ƒ��A���ڗS�q���j
�@������A�ӂƉ�ɕԂ�A�������ɂ��Ôg������Ǝv���A�}���őD��z�`����o���A�����V���ɌW�������B�����ď��h�c���Ƃ��č`�ɖ߂�A���g�h�~�̃Q�[�g��߂��B�Ƒ��ƎԂ�����ɔ������̂��A�`�ɏW�܂蒪�ʂ̕ω�����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���犈����ʂ��x��
�@�Ôg�ɂ�薽����Y���D���A�����ЊQ�ɂ���̌����Ȃ��ɂȂ��Ă��鍡�A���������������Z���^�[�ł́A��Ђ��ꂽ�n��̕����ɂ͒����Ԃ�v���ƍl���A�������ɂ킽��ЊQ�x�������Ƃ��āu���犈���v��ʂ����ЊQ�x�����s�������ƍl���Ă���B
�@����͎�����������܂ŏ\��N�ԍs���Ă����A�������̌��w�K�̃m�E�n�E�����p�����x���Ƃ������ƂɂȂ�B�P�Ȃ�a�J��ł̏Z���̒ł͂Ȃ��A���R�w�Z�Ƃ��Ă̍��������Z���^�[�̓��ӕ���ŁA��Ђ��ꂽ���X�A���Ɏq�ǂ�������S�I�X�g���X����J�����A�����������펞�̐��������߂��A�w�Z�ł̎��Ƃ�����悤�ɂ������B
�@�Ôg�̋��|�ɂ��C�������悤�ɂȂ����q�ǂ������ɂ��܈�x�A�C�̂��炵����`�������B�����̔������C�ŁA�q�ǂ������̐S�̃P�A���ł��Ȃ����̂��Ǝv���̂��B

�����Z���^�[���s���Ă���V���m�[�P�����O�̌��B�C�Ŏq����̐S�̃P�A���ƍl���Ă���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƒ�������
�@��̓I�ɂ͌��ݑ匎�����炨�肵�Ă��鋌�������w�Z�̋������������A���~���ɂ��Ă��镔���i�ꋳ�����Ɏd��������\������j���l�����قǎq�ǂ��ƉƑ��ɖ����Œ���B���Ԃ͍Œ���N�ԁB���ƒ�Ȏ����g���Ď������Ă��炤�B���C������̂ŋ��p�Ŏg���Ă��炤�B�q�ǂ��̐��ɂ���Ă͋��p�̕��������p�ӂ�����肾�B
�@���̑��A�N�Ԃ�ʂ��ĊC��R�ł̊��w�K�A�̌��v���O��������A�q�ǂ��������y�����߂������Ƃ��ł���悤�ɂ������B�h�юs�ł����c�Z������Ɛ\���o�Ă��������Ă���̂ŁA������ɉz���Ă����q�ǂ������ɂ����v���O�������Œ������ƍl���Ă���B
�@��C�n�k���z�肳��鍂�m���̊C�ݕ��ւ̔��ɂ��Ă͎^�ۂ����낤���A�C���瓦���邾���łȂ��C�Ƃ̂����������w�Ԏ����d�v�ƍl���A�Ôg�ЊQ�ɑ��������������Ă��������Ǝv���Ă���B����ɂ��Ă͎��̂g�o���Q�Ƃ�������(http://www.orquesta.org/kuroshio/)�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��C�n�k�ɔ����}�b�v
�@�����Z���^�[�ł͐��N�O����A�߂������N����Ƃ�����C�n�k�ɔ����A����܂ł������̌v�������Ă����B
�@�����ɂ͓�̒n�悪����A�����n��ł́u�������w�Z�v�A�n����n��ł́u�R�̐_�v�A�u�c������̔��v�̂R�J�������ꏊ�Ɏw�肳��Ă���B�����́A�ǂ��ɓ����邩���F�m���Ă���B�������A�ߔN�吨�K��郌�W���[�q��ό��q���͂����ĕ����邾�낤��?
�@�ȑO�_�C�o�[�ɃA���P�[�g���������A���N�����s�[�^�[�Ƃ��ė��Ă���l�����ł����A�C�ƃ_�C�r���O�V���b�v�Ɨ��فE���h�����s�������Ƃ��Ȃ��A�����������������Ƃ͂Ȃ��Ƃ̉��قƂ�ǂ������B�m���ɔ��ꏊ�u�c������̔��v�Ƃ����Ă��A����ǂ�?�Ǝv�����낤�B

���ꏊ�������Ŕu�c������̔��v�B������Ăǂ��H�i�匎�������A�~�����C�����j
�@���ʃz�e���Ȃǂł͊e�����ɕK�������Ɣ��o�H���������n�}��p���t���b�g���u����Ă���A�`�F�b�N�C���̍ۂɃt�����g�Ŋm�F����悤���肢�����B�ό��q���吨����Ƃ���ł���A�����������O������̂��q����ɑ�������͐�ɕK�v���Ǝv���B���݃Z���^�[�ł͂������������ꏊ���L�������łȂ��A���S�Ȕ��o�H�����ē������}�b�v���쐬���ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�݂̑ϐk�⋭��
�@���i�Ȃ�ŒZ�R�[�X�ōs���铹���A�n�k������u���b�N���̓|��⊢�̗����Ȃǂ��z�肳��A�����ɂ悭����ׂ��H�n�͂��ꂫ���U�����Ēʂ�Ȃ��\��������B�q�ǂ��₨�N���͏��z���čs���͓̂���A���ɒʂ�Ă��Ôg���B�܂ł̒Z�����ԓ��̔��͕s�\���낤�B

�����W���ɑ��������H�n�i�����j
�@�܂��C�݉��̍L�����H���ړ����悤�Ƃ��Ă��A�W������邽�߂̖h���炪�f���������邽�߈ړ��ł��Ȃ��B�����n���s���Ƃ����͂��ėL���Ȕ��o�H�̊m�ۂ�A�|��̉\���̂���悤�ȃu���b�N���̕⋭�Ȃǂ����Ă����K�v������B
�@�������ӂ܂�����ł̔��}�b�v�����A�S�ˁA����і��h�E���فA�_�C�r���O�V���b�v�ƂȂǂɂ��z�z���悤�ƍl���Ă���B���������ꂾ���ł͕s�\���ł���B�����瓪�ŕ������Ă��Ă������������P�������Ă��Ȃ���A�����Ƃ����Ƃ��ɖ��ɂ͗����Ȃ����낤�B
�@�k�Ђ̗����A��̑��q�̎�������āA����甐�����w�Z�܂ł̔��H������Ă݂��B�����Ȃ���A�����̕��͊댯�ł͂Ƃ��A���̓��͋����Ċ��������Ă������ɕ����Â炭�Ȃ����A��ԏƖ����Ȃ��Ƃ��ɂ͂ǂ����邩�Ȃǂƃ`�F�b�N�����ĉ�����B�����Ă���Ƃ̎v���ō���ɂ��鏬�w�Z�ɍs���������B�����A���N�p�Z�ƂȂ����������w�Z�͔��ꏊ�Ɏw�肳��Ă͂��邪�A�Z�ɂ̑ϐk�����ۏႳ��Ă��Ȃ��B
�@���{�݂��|�Ă��܂����瓦���ꂪ�����Ȃ�B�匎�������łȂ��S���̎����̂ł͊w�Z�����ꏊ�Ƃ��Ďw�肳��Ă���Ƃ��낪�����B�����������Ƃ���̑ϐk�����Ѝ��A���ɂ��l���Ă������������B�������A�ł��d�v�Ȃ��Ƃ́A�Z������̐S�\���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Z���^�[���E�_�c�D�j
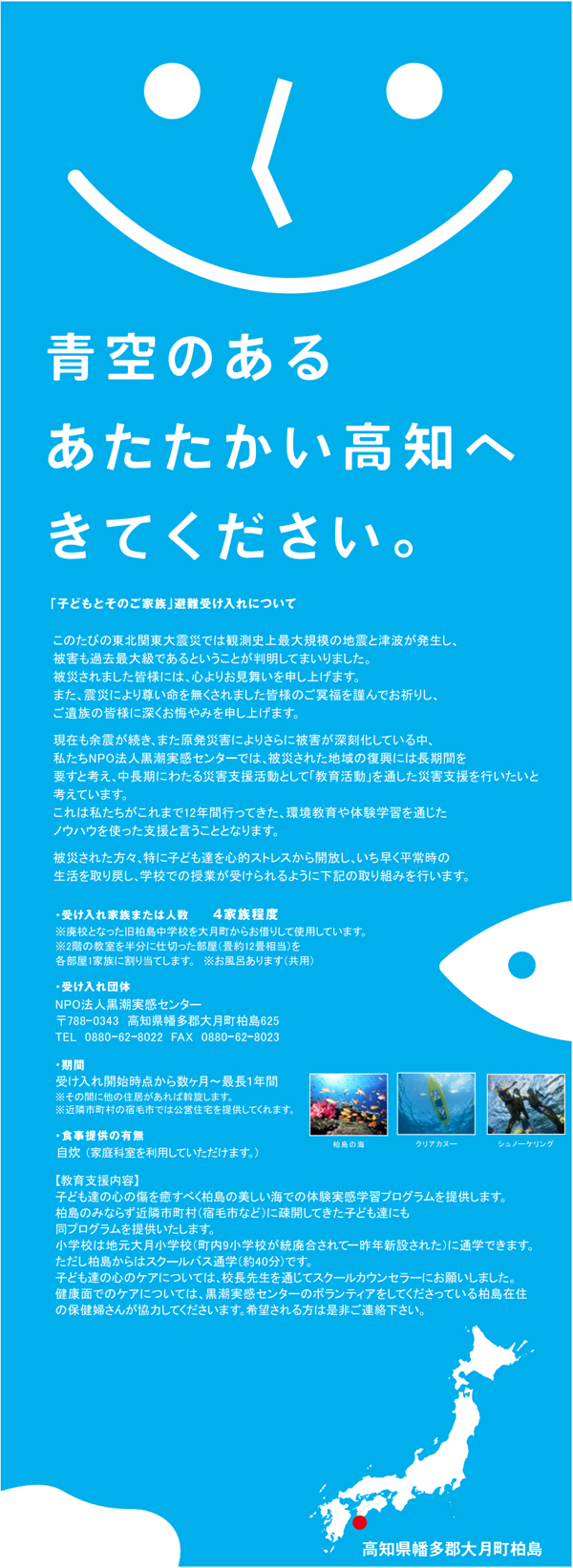
��Вn�̎q��ɍ��m�ɑa�J���Ă��Ă��炨���Ƃ̎v�������߂č�����E�F�u�|�X�^�[�̈ꕔ�i���́E�~���f�U�C���������j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Ђ����q��𔐓���
�@�܂��ŏ��ɁA�����{��k�ЂŔ�Ђ��ꂽ�F�l�ɁA�S��肨��������\���グ�A�܂��A�S���Ȃ�ꂽ�F�l�̂����������F�肵�܂��B�����č���́A���������������Z���^�[���l�����s���悤�Ƃ��Ă���A��Ђ����q�ǂ���̎���Ȃǂ́A�ЊQ�x�������Ȃǂɂ��ĕ��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ռ��̉f��
�@3��11���ߌ�2��46���B���̓��̔����́A���͂�����̂̕��i�ƕς��Ȃ������B�������͎������Ŏd�������Ă����B�X�^�b�t�̉�������̌g�т������B���Ɍ��ɏZ��ł���ޏ��̉Ƒ����炾�����B�u�������n�k�������ăe���r��������A���k�ő傫�Ȓn�k���������݂��������ǁA�������͑��v�H�v
�@�}���Ńe���r�������B���{�n�}���\������k���݈�ɒÔg�x���߂���A�A�i�E���T�[�����ӂ��Ăт����Ă����B�e���r��ʂ͋{�錧�̋��`���ӂ̊C���f���Ă����B���������̂Ƃ��낪�h��Ȃ������������A����قǑ傫�ȒÔg������Ƃ͎v�������Ȃ������B
�@����������A���ʂ��������ɍ����Ȃ�ݕǂ��痤�ɐ����͂��オ���Ă����B����悠���Ƃ����Ԃɑ傫�ȒÔg�����X�ɉ����A��^���D��A���D�̌W�����[�v����A�D�����X�Ɨ����ꗤ�ɑł��グ��ꂽ�B���̌�Ƃ�ԁA����Ƃ�������̂��u���Ԃɍ����g�ɂ̂ݍ��܂�A�|�M�������i��ڂɂ����B
�@����͍��A�{���ɓ��{�ŋN���Ă��邱�ƂȂ̂��H�ɂ킩�ɂ͐M�����Ȃ������B���X�Ɖf���o�����Ռ��̉f���ɖڂ������t���ɂȂ�A�e���r�̑O���痣����Ȃ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����{��k�Д�Вn�̗l�q�B�����̏�Ɏ��c���ꂽ�A���D�@�@�@�@�@�@�@�@�i��茧��ƒ��A���ڗS�q���j
�@������A�ӂƉ�ɕԂ�A�������ɂ��Ôg������Ǝv���A�}���őD��z�`����o���A�����V���ɌW�������B�����ď��h�c���Ƃ��č`�ɖ߂�A���g�h�~�̃Q�[�g��߂��B�Ƒ��ƎԂ�����ɔ������̂��A�`�ɏW�܂蒪�ʂ̕ω�����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���犈����ʂ��x��
�@�Ôg�ɂ�薽����Y���D���A�����ЊQ�ɂ���̌����Ȃ��ɂȂ��Ă��鍡�A���������������Z���^�[�ł́A��Ђ��ꂽ�n��̕����ɂ͒����Ԃ�v���ƍl���A�������ɂ킽��ЊQ�x�������Ƃ��āu���犈���v��ʂ����ЊQ�x�����s�������ƍl���Ă���B
�@����͎�����������܂ŏ\��N�ԍs���Ă����A�������̌��w�K�̃m�E�n�E�����p�����x���Ƃ������ƂɂȂ�B�P�Ȃ�a�J��ł̏Z���̒ł͂Ȃ��A���R�w�Z�Ƃ��Ă̍��������Z���^�[�̓��ӕ���ŁA��Ђ��ꂽ���X�A���Ɏq�ǂ�������S�I�X�g���X����J�����A�����������펞�̐��������߂��A�w�Z�ł̎��Ƃ�����悤�ɂ������B
�@�Ôg�̋��|�ɂ��C�������悤�ɂȂ����q�ǂ������ɂ��܈�x�A�C�̂��炵����`�������B�����̔������C�ŁA�q�ǂ������̐S�̃P�A���ł��Ȃ����̂��Ǝv���̂��B
�����Z���^�[���s���Ă���V���m�[�P�����O�̌��B�C�Ŏq����̐S�̃P�A���ƍl���Ă���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƒ�������
�@��̓I�ɂ͌��ݑ匎�����炨�肵�Ă��鋌�������w�Z�̋������������A���~���ɂ��Ă��镔���i�ꋳ�����Ɏd��������\������j���l�����قǎq�ǂ��ƉƑ��ɖ����Œ���B���Ԃ͍Œ���N�ԁB���ƒ�Ȏ����g���Ď������Ă��炤�B���C������̂ŋ��p�Ŏg���Ă��炤�B�q�ǂ��̐��ɂ���Ă͋��p�̕��������p�ӂ�����肾�B
�@���̑��A�N�Ԃ�ʂ��ĊC��R�ł̊��w�K�A�̌��v���O��������A�q�ǂ��������y�����߂������Ƃ��ł���悤�ɂ������B�h�юs�ł����c�Z������Ɛ\���o�Ă��������Ă���̂ŁA������ɉz���Ă����q�ǂ������ɂ����v���O�������Œ������ƍl���Ă���B
�@��C�n�k���z�肳��鍂�m���̊C�ݕ��ւ̔��ɂ��Ă͎^�ۂ����낤���A�C���瓦���邾���łȂ��C�Ƃ̂����������w�Ԏ����d�v�ƍl���A�Ôg�ЊQ�ɑ��������������Ă��������Ǝv���Ă���B����ɂ��Ă͎��̂g�o���Q�Ƃ�������(http://www.orquesta.org/kuroshio/)�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��C�n�k�ɔ����}�b�v
�@�����Z���^�[�ł͐��N�O����A�߂������N����Ƃ�����C�n�k�ɔ����A����܂ł������̌v�������Ă����B
�@�����ɂ͓�̒n�悪����A�����n��ł́u�������w�Z�v�A�n����n��ł́u�R�̐_�v�A�u�c������̔��v�̂R�J�������ꏊ�Ɏw�肳��Ă���B�����́A�ǂ��ɓ����邩���F�m���Ă���B�������A�ߔN�吨�K��郌�W���[�q��ό��q���͂����ĕ����邾�낤��?
�@�ȑO�_�C�o�[�ɃA���P�[�g���������A���N�����s�[�^�[�Ƃ��ė��Ă���l�����ł����A�C�ƃ_�C�r���O�V���b�v�Ɨ��فE���h�����s�������Ƃ��Ȃ��A�����������������Ƃ͂Ȃ��Ƃ̉��قƂ�ǂ������B�m���ɔ��ꏊ�u�c������̔��v�Ƃ����Ă��A����ǂ�?�Ǝv�����낤�B
���ꏊ�������Ŕu�c������̔��v�B������Ăǂ��H�i�匎�������A�~�����C�����j
�@���ʃz�e���Ȃǂł͊e�����ɕK�������Ɣ��o�H���������n�}��p���t���b�g���u����Ă���A�`�F�b�N�C���̍ۂɃt�����g�Ŋm�F����悤���肢�����B�ό��q���吨����Ƃ���ł���A�����������O������̂��q����ɑ�������͐�ɕK�v���Ǝv���B���݃Z���^�[�ł͂������������ꏊ���L�������łȂ��A���S�Ȕ��o�H�����ē������}�b�v���쐬���ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�݂̑ϐk�⋭��
�@���i�Ȃ�ŒZ�R�[�X�ōs���铹���A�n�k������u���b�N���̓|��⊢�̗����Ȃǂ��z�肳��A�����ɂ悭����ׂ��H�n�͂��ꂫ���U�����Ēʂ�Ȃ��\��������B�q�ǂ��₨�N���͏��z���čs���͓̂���A���ɒʂ�Ă��Ôg���B�܂ł̒Z�����ԓ��̔��͕s�\���낤�B
�����W���ɑ��������H�n�i�����j
�@�܂��C�݉��̍L�����H���ړ����悤�Ƃ��Ă��A�W������邽�߂̖h���炪�f���������邽�߈ړ��ł��Ȃ��B�����n���s���Ƃ����͂��ėL���Ȕ��o�H�̊m�ۂ�A�|��̉\���̂���悤�ȃu���b�N���̕⋭�Ȃǂ����Ă����K�v������B
�@�������ӂ܂�����ł̔��}�b�v�����A�S�ˁA����і��h�E���فA�_�C�r���O�V���b�v�ƂȂǂɂ��z�z���悤�ƍl���Ă���B���������ꂾ���ł͕s�\���ł���B�����瓪�ŕ������Ă��Ă������������P�������Ă��Ȃ���A�����Ƃ����Ƃ��ɖ��ɂ͗����Ȃ����낤�B
�@�k�Ђ̗����A��̑��q�̎�������āA����甐�����w�Z�܂ł̔��H������Ă݂��B�����Ȃ���A�����̕��͊댯�ł͂Ƃ��A���̓��͋����Ċ��������Ă������ɕ����Â炭�Ȃ����A��ԏƖ����Ȃ��Ƃ��ɂ͂ǂ����邩�Ȃǂƃ`�F�b�N�����ĉ�����B�����Ă���Ƃ̎v���ō���ɂ��鏬�w�Z�ɍs���������B�����A���N�p�Z�ƂȂ����������w�Z�͔��ꏊ�Ɏw�肳��Ă͂��邪�A�Z�ɂ̑ϐk�����ۏႳ��Ă��Ȃ��B
�@���{�݂��|�Ă��܂����瓦���ꂪ�����Ȃ�B�匎�������łȂ��S���̎����̂ł͊w�Z�����ꏊ�Ƃ��Ďw�肳��Ă���Ƃ��낪�����B�����������Ƃ���̑ϐk�����Ѝ��A���ɂ��l���Ă������������B�������A�ł��d�v�Ȃ��Ƃ́A�Z������̐S�\���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Z���^�[���E�_�c�D�j
�X�V�F
Kanda
/2011�N 06�� 30�� 08�� 47��
